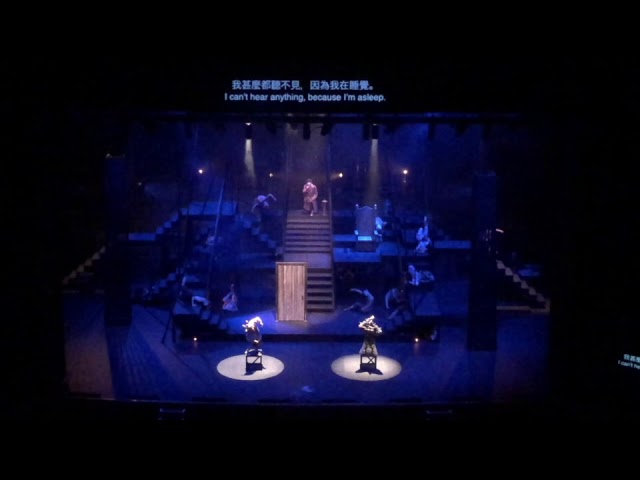万有引力 第8回公演 幻想音楽劇 草迷宮 -てんてん草紙ー (1986)
1986年5月3日(土)~5月6日(火) 第8回公演
幻想音楽劇
草迷宮
―てんてん草紙―
会場
渋谷シードホール
料金
前売り1500円 当日1800円
スタッフ
原作
泉鏡花
台本
寺山修司
構成・演出・音楽
J・A・シーザー
美術
ツール・ヴァーグ 山岸学雄
美粧
上海綾子 ナカタケイコ
音響
落合敏行
照明
佐藤啓
舞台監督
松田将希
制作
大澤由喜 松田将希 佐藤啓 永地イケヤ
照明協力
丸山邦彦 C・A・T
キャスト
サルバドール・タリ 根本豊 矢口桃 水岡彰宏 高田恵篤 中村亮 海津義孝 松丸純子 ナカタケイコ
袴田貴子 中山信弘 須崎晃 増根雄次 清原昭彦 出口容子
解説
「アウト・オブ・マン=外套の異邦人」から半年ぶりに演劇実験室◎万有引力が挑む幻音楽劇「草迷宮」!! この作品は1978年に上演された説教節の主題による見世物オペラ「身毒丸」の第二弾として準備されていたもので 「母を生涯の女とした思慕が手毬唄、謎唄となって主人公を迷宮へ誘ってゆく。二度と帰ることのできないその球体に 憑かれた少年は、その内環構造のなかへ!!」という鏡花の原作を、1978年寺山修司によって「少年のとり憑かれた球体が、 手毬から母の乳房へと換喩されながらオイデプスの病んだ《私という病=私迷宮=どこまでいっても同じ場所だ というトートロジーの世界》」として映画化された。そして1986年!万有引力によって初の舞台化が 実現しようとしている。
てんてん手毬に誘われて、着いたところは母地獄!!吹くや謀叛の手毬唄!! 無惨なまでに魂麗の花びらを零し続けた泉鏡花の「草迷宮」に材を選び、子供世界の応答地獄・生まれ変わって「別の母」を 探す迷宮譚、人間謎と手毬唄!寺山修司の遺した19枚の台本をもとに遂に万有引力が舞台化!!
芋蔓の葉を被った女は、狐とも狸とも姑獲鳥とも異体の知れぬ不思議女。癩か?痘痕の幽霊か?もしや、私の探している 母さんでは!!と尋ねる水岡彰宏、高田恵篤、中村亮、海津義孝の四人で一人の主人公、明。 なき母の矢口桃はいつしか劇全体の比喩となり七変化で劇を舞う。円環地獄の根本豊の水先案内人は子産石を生首に 変え、サルバドール・タリの他国の男は猫の死骸を懐に抱き、松丸純子の魔性の菖浦が手毬つく!!万有引力が 総力で、初めて挑む呪術音楽による語りものの実験。あっ!乳母の背中から見た祭礼の町が!!
想像力を刺激し、聞き手《観客》が参加する範囲も広かったといわれる《語り物世界》、パラゴロ二十人衆の音曲詩!!
現代演劇、とくに実験劇というものがはたす役割が稀薄化し、それにともない観客も宿命的な紐帯としても考えられなくなって しまったのではないだろうか。したがって、もともと日本にあった観客参加、実験劇の原型とも言える《語り物世界》に触れる ことによって現代演劇から失われゆく《劇的なるもの》を若手俳優、スタッフ、そして観客とともに呼び戻し、時代の流れや 渦中にひきずり込まれる演劇ではなく、少なくとも時代の船首より一歩でも先行する演劇を目指しながら、 今、なぜ語り物なのかを考えてみたい。 「そして、また例のほら穴をたずねることになった。というのは私が十三才の時、九州、坪谷の天険のほら穴に《母の子守り唄辞典》という、不思議な生きた画集を見つけたことがあるからである。それは地面から三十センチほど顔を出した本で、地に埋まって いる部分は、とても深く埋まっていたのを覚えている。私が困った時に、私の魂はいつもそのほら穴をたずね、無限の厚さを 持ったその本から《心象》を捧かってくるのである。それは音楽のみにとどまらず私のすべてのためにある《絵空辞典範》だったのである。」 (私の紫魂歌があなたをオペラ迷宮に誘い込む、説教節「身毒丸」のための 6000字)と1978年の天井桟敷新聞に書いたことがあるが、真実、私が作曲する場合この本をたずねることが多い。 もしくは離人体験=自己像幻視=多重人格=もう一人の私と一緒にといった摩可不思議な方法が私にとっては普通であるというと 「きもち悪い」「嘘つき」と思う輩が大勢いるのも事実である。しかし、音の出所なんてのは蓄積(記憶)できないのである。 つまり、もう一人の自分(他人?)が意識できないとできない作業ではないのだろうかと本気で思っている私はやはりオカシイ 人なのかも知れない。
地の果てに望郷ありとたづねきて、手毬つきつゝ狂ひゆかんか(寺山修司)
「母の腹から生まれたが、母はほかにいる」ということの転生の思想。十月十日の母胎の中で、その人はすでに人生(歴史)を 完成させるのではないだろうか。そして胎外へ出た時、肉体化されたその体験は知識、教育という関係言語世界で 自己像幻視=多重人格という幻の世界の人として扱われてしまうのである。「少年時代の《私》は母親のそばにいて、その 少年の成長(この時期、多くの知識を強制される)した《私》に母がいなくななっている」ということにもなる。
棺桶にしまひ忘れし手毬ゆえ 五色の糸の行方知れず(寺山修司)
「母子関係でも父子関係でもよい姉妹関係でも兄弟関係でもよい、ようは関係を確認し儚い安心感の上で眠りたいのだ…」 鏡花のかなしい切実な《関係ごっこ》!「血による因縁関係ではなく自分の選び出した新しい関係つまりあらゆる関係は つねに《ある》ものではなく《作られる》ものであり、親と子の問題もまた、けっして例外ではないのである。」と寺山修司。 そして《母》とはつねに《幻》でしかなかったのではないか! ああ母恋しや!! この作品は、もともと大正時代のオペラにあつまったゴロツキども、つまり《ペラゴロ》とその時代の見世物小屋のある町の風景、 ジンタの音楽、活動写真に《いい空気》のイメージがあったので、舞台は浅草のキャバレー跡でと考えていた。客席に生えた ぺんぺん草の香りと生命力の中で人間転生譚の空の広さのことをすっかり見落している》という寺山修司のことばと 《自分の満足と欠陥から成る外側のあらゆるもの》とした万有引力思想が引き合いながら「演劇の地平」をさらに深く 切り裂こうとしている。
J・A・シーザー